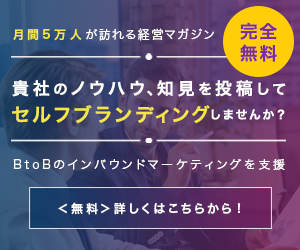不当利得(ふとうりとく)とは、契約などのような法律上の原因がないにもかかわらず、本来利益が帰属すべき者の損失と対応する形で利益を受けること(利得すること)、またはその受けた利益(利得)そのもののこと。またはそのような利益が本来は帰属すべきだった者に対して自身が得た利益(利得)を返還させる法理あるいは制度(不当利得法、不当利得制度)のこと。日本の民法においてはb:民法第703条|民法703条からb:民法第708条|708条に規定されている。契約、不法行為、事務管理とならぶ民法上の債権発生原因の一つである。
*民法について以下では、条数のみ記載する。
==適用場面==
不当利得が適用される典型的な場面は、一度有効に成立した契約が無効であったり、取消|取り消されたりして「初めからなかったもの」とされた場合である。例えば、カメラを5万円で買う契約を結び、買主は代金と引き換えに売主からカメラを受け取ったが、後になって買主が錯誤による契約の無効を主張した、とする。すると契約は「初めからなかったこと」になるので、売主は「契約」という法律上の原因なしに代金を所持していることになり、買主は支払った代金分の「損失」を被っていることになる。そこで買主は不当利得の制度に基づいて売主に対し代金の返還を請求できる。もちろん、売主の方も不当利得制度によってカメラを返還するように請求できる。これが不当利得制度の想定する典型的な場面である。
==一般の不当利得==
不当利得について原則的な処理方法が記述されているのは703条とb:民法第704条|704条である。そこでこれを一般不当利得と呼ぶことがある。これによれば、不当利得とは、法律上の原因なしに他人の財産又は労務により利益を受けている者(受益者という)から、これによって損失を被っている者に対して利得を返還させる制度であると規定されている。
法律上の原因がないのに利益を受けていることについて知らなかった者(善意の受益者)は利益の存する限度(現存利益)でその利得を返還しなくてはならない(不当利得に基づく返還請求は原則として全額の返還であるとする考え方からすれば、「善意者は現存利益の返還のみで足りる」と言う方が正確である)。これは、問題となっている利得が自己に帰属していると信じていた場合、その信頼を保護する必要があると考えられるためである。
一方、不当利得であると知りながら利益を得ていた者(悪意の受益者)は受けた利益に法定利息をつけて返還する必要があり、場合によっては損害賠償責任(これは不法行為に基づく損害賠償請求であるとされている)をも負うことになる。これは、悪意の受益者は当該利益を保持することができる法律上の原因が自己にないことを知っている以上、利得を返還することまでを計算に入れておくべきであるから、他人の財産を管理するのと同等の注意をもって当該利得を管理することが義務付けられることに由来する。
出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 GNU Free Documentation License.
経営に関する人気コラム一覧
ビジネス用語・経営用語辞典カテゴリ
- 経営や企業に関する用語
- 営業・集客などのマーケティング用語
- 経営関連の法律・制度の用語
- 経理や会計に関する用語
- 財務や経理に関する用語
- 税金に関する用語
- 組織やマネジメントに関する用語
- 年金・保険・労務に関する用語
- 投資や債権に関する用語
- ISOや規格に関する用語
- 基礎経済知識に関する用語
経営者支援コンテンツ
会員メニュー
会員限定のメニューです
気になったページのMyリストへの登録や、経営に役立つ情報メルマガの管理など、さまざまな便利機能がご利用いただけます



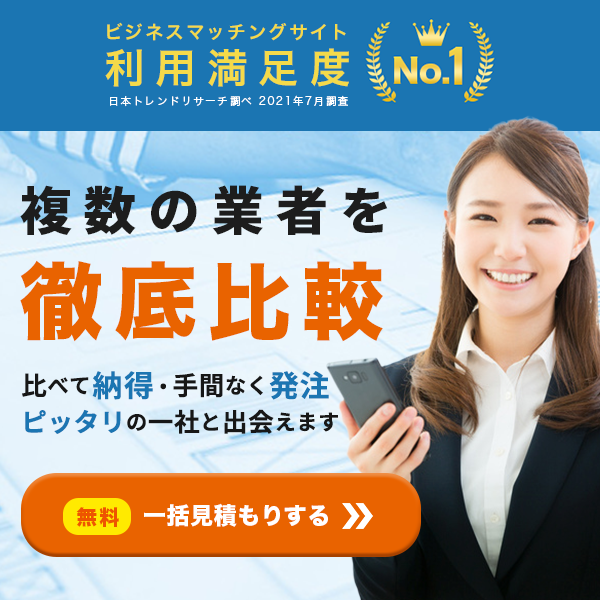
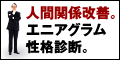 ビジネス向けの無料性格診断で上司と部下の人間関係改善
ビジネス向けの無料性格診断で上司と部下の人間関係改善