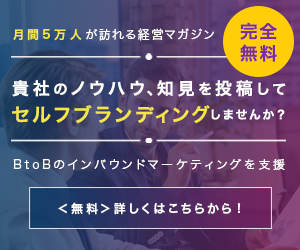法定実効税率(ほうていじっこうぜいりつ、英:normal effective statutory tax rate)とは、課税所得に対する法人税、住民税、事業税の表面税率に基づく所定の算定式による総合的な税率をさす。税効果会計における繰延税金資産、繰延税金負債は、一時差異に法定実効税率を乗じて算定される。
== 概要 ==
本来であれば、法定実効税率は、法人税率、事業税率、住民税率を単純に合算した合計税率と一致するはずである。しかしながら、第一に、合計税率の構成主体のうち住民税の課税標準額は、課税所得ではなく法人税額を基礎としている(他の2者は課税所得を基礎としている)。第二に、法定実効税率の構成主体のうち、事業税は、支払事業年度の課税所得算定上損金算入が認められている。これら2点を勘案する必要があるため、実際の税負担率は単純合算値よりも小さくなる。
これらをふまえ、数式で表示すると、以下の算定式が導かれる。
:合計税率 = 法人税率 + 法人税率 × 住民税率+事業税率(住民税率は、法人税率を乗じた影響にとどまる)
:法定実効税率 = 合計税率 − 事業税率 × 法定実効税率(事業税率は、法定実効税率を割り引いた影響にとどまる)
:法定実効税率 = 〔法人税率×(1+住民税率)+事業税率〕÷(1+事業税率)
例えば、表面税率が法人税率:30% 住民税率:17.3% 事業税率:9.6%の場合、法定実効税率は以下の数値となる。
:法定実効税率 = 〔0.3×(1+0.173)+0.096〕÷(1+0.096)≒40.86%
== 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等負担率との不一致要因 ==
理論上の法定実効税率と実際に企業の負担する税効果会計適用後の法人税等負担率は、大抵の場合一致しない。その要因は様々であるが、主な要因としては、以下のものがある。
法定実効税率が課税所得を基礎とするのに対し、税効果会計適用後の法人税等負担率は企業会計上の税引前当期純利益を基礎としている。元々両者間では、交際費などの永久差異が一致しないため、差異原因となる。
将来減算一時差異のうち、将来回収される可能性が低く、課税所得と対応させることができないスケジューリング不能な一時差異と判断される場合。繰延税金資産の計上が認められず、評価性引当額として控除されるため、永久差異と同様に両者間の差異原因となる。
== 諸外国と比較した法定実効税率の水準について ==
海外と比較して、日本の法定実効税率は重いとする指摘がしばしばされている。これについて、財務省 (日本)|財務省統計資料によると、2006年1月現在の日本の法定実効税率は40.69%である。これは、米国やドイツ(いずれも40%〜45%台)とほぼ同水準であり、フランスの33%、イギリスの30%と比較すると、先進国の中では高い水準である。<ref>ただし、EU加盟国間では、EU法の施行により間接税に関する標準税率を、原則15%以上とすることが求められているため、フランス、イギリスの間接税負担は、日本の消費税(5%)と比して3倍以上の水準である。したがって、租税負担を議論する際は、法人への直接的な負担だけでなく、家計等への間接的な負担を含め、総合的に勘案する必要がある。また、高福祉の推進を国策とする国々(北欧等)では、税負担も相応に高くなる傾向があるため、税負担の国際比較を行う際には、各国の福祉・経済政策の両面を考慮する必要があるといえよう。</ref>このため、経団連等の財界を中心に、さらなる実効税率引き下げを要望する声が強い。
一方、厳しい財政状況の中、さらなる法定実効税率引き下げによる減収を消費税引き上げ等、他の税制により減収を補わなければならなくなるという実情や、引当金制度や外国税額控除等を含めると実際の個別の企業の税負担は低い場合もあり、単純には比較できないという指摘もある。
また、一般論として日本より実効税率の低いフランスでは従業員の年金や健康保険等の社会保険料を企業が日本の場合より
多く負担しており、税と社会保険料を含めた企業の負担を計算すると日本の方が高いという事実もあり、実効税率だけの比較で日本企業の負担が諸外国より多いとする主張は明確に誤りだとする議論も存在する。
出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 GNU Free Documentation License.
経理・財務に関する人気コラム一覧
ビジネス用語・経営用語辞典カテゴリ
- 経営や企業に関する用語
- 営業・集客などのマーケティング用語
- 経営関連の法律・制度の用語
- 経理や会計に関する用語
- 財務や経理に関する用語
- 税金に関する用語
- 組織やマネジメントに関する用語
- 年金・保険・労務に関する用語
- 投資や債権に関する用語
- ISOや規格に関する用語
- 基礎経済知識に関する用語
経営者支援コンテンツ
会員メニュー
会員限定のメニューです
気になったページのMyリストへの登録や、経営に役立つ情報メルマガの管理など、さまざまな便利機能がご利用いただけます




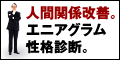 ビジネス向けの無料性格診断で上司と部下の人間関係改善
ビジネス向けの無料性格診断で上司と部下の人間関係改善