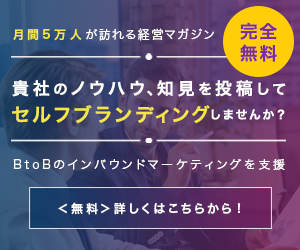ある会社を訪問して、原価を担当している方(経理部門)とお会いしたときのことです。
「先生、標準原価に対する実績原価の差異分析を一般の会社では、どのように進めているのですか。」との質問を受けました。
この質問に対して私は、「貴社では、どのように進められているのですか。」と回答せずに、質問を返しました。
すると、その会社では、直接材料費と直接労務費、製造間接費に分け、原価差異分析を行い、工場にフィードバックしているそうです。
しかし、工場では、あまり活用されていないようなので、もっと有効に活用して欲しいのだということでした。
その後、彼は、数量差異と価格差異に分けて云々・・・。と詳しく説明をしてくれました。
貴社では、どのように進められていますか。
私の回答は、簡単なものでした。
何故、経理で原価差異分析の情報を作成し、工場に提供するのですか。
生産が完了して、時間が経過してから原価情報をもらっても、工場は、ただ眺める程度にしかならないでしょう。
問題が発生した時点で、対処しなければ役に立たないのではないでしょうかと答えました。
すると彼は怒って、だったらどうすればいいんですかと強い口調で言ってきました。
原価統制を考えるときには、工場にいる作業者がすぐに問題を発見でき、改善する仕組みを持つことです。
材料費を考えますと、材料費には、材料の価格差異と数量差異があります。材料の価格差異は、購買部門での調達価格の違いによるものです。
一方、数量差異は、生産現場での材料取りのミス、不良などが考えられます。
そして、これら差異の原因に対する責任部門は明らかであり、金額ではないが、ほかに置き換えられる数字で把握できます。
つまり、置き換えられるこれらの数字に対する提示をして、差異の発生を作業者自信が認識できる仕組みを持つことが大切ではないでしょうか。
具体的に、直接労務費を考えて見ましょう。
直接労務費は、賃率と作業時間の差異に分けることができます。
この2つの責任部門はどこになるでしょうか。
まず賃率を考えますと、標準原価、実績原価ともに一般に予定賃率を用いていますから、この項目での差異は発生しないでしょう。
つぎに作業時間を考えますと、標準時間に対する実績時間となりますから、現場の作業者に起因する習熟度、作業手順の間違い、異常作業の発生などが考えられます。
つまり、生産現場の作業者に対して、標準時間を提示できれば有効であるということになります。
ただし、ここで注意していただきたいことがあります。
それは、標準時間の設定です。
標準時間は、作業標準にのっとって設定されます。得てして測定した実績時間を標準時間だとして使ってしまうことがあります。
これでは、標準時間と実績時間での差異は、ほとんど発生しないか、毎回大きく異なり、役に立たないと考えてしまうからです。
最後に間接費について考えてみます。
製造間接費に関して、差異分析をするということですが、これはあまり意味のあることではないでしょう。
何故ならば、標準間接費は標準時間に間接費率を乗じて求められるからです。
つまり、原価統制で検討すべきは、作業の時間ということなのです。
今回は、一般に言われる原価計算の視点から述べてきました。
私は、原価統制を前面に押し出して考えるよりも、まず全社員のコスト意識を高めることが大切であると思います。
そして、各部門であり、担当者が、コストに関して自分たちの担っている役割と責任の大切さを理解できるようにすることです。
このことを考えずに、コストダウンを進めても、多くの効果は得られないのではないでしょうか。
製品のコストダウンをどのように進めたらよいのか企業の第一の目的は、利益の獲得にあります。その経営活動は、結果として数字で表れされます。企業が、維持存続し、成長していくためには、この数字のからくりを理解し、経済性を高めることが大切です。それは、ただ数字を眺めているだけでは分かりません。やはり、経営活 …
最近投稿された他のコラム
会員メニュー
会員限定のメニューです
気になったページのMyリストへの登録や、経営に役立つ情報メルマガの管理など、さまざまな便利機能がご利用いただけます


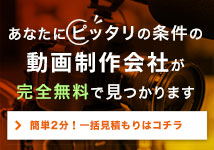
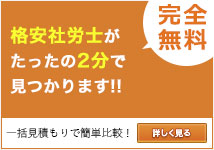


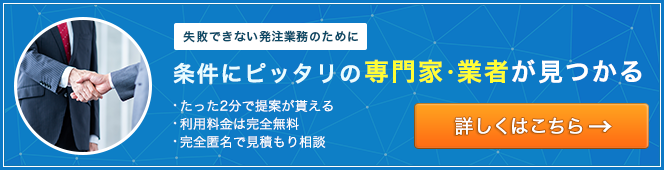
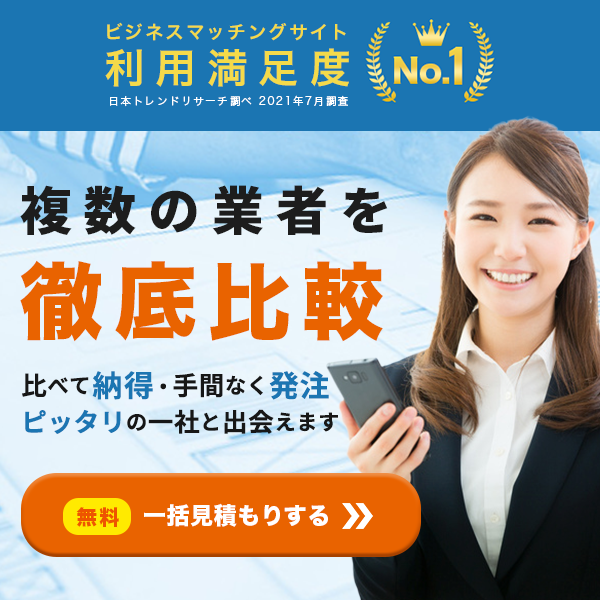
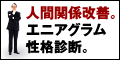 ビジネス向けの無料性格診断で上司と部下の人間関係改善
ビジネス向けの無料性格診断で上司と部下の人間関係改善