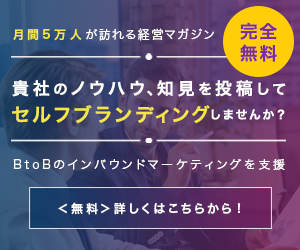職務発明(しょくむはつめい)とは、「従業者等」(会社の従業員など)が職務上行った発明のことであり、「使用者等」(会社など)は職務発明を発明者である従業員から承継することを勤務規定などによってあらかじめ定めておくことができる(特許法35条2項の反対解釈)。会社が従業員から職務発明を承継した場合、会社は相当の対価を従業者に支払わなければならない(特許法35条3項)。
この規定に基づいて会社に対して200億円の支払いを命じる判決がでたこともあり(東京地裁平成16年1月30日判決「発光ダイオード青色発光ダイオード|青色発光ダイオード事件」、その後高裁で和解。詳しくは後述)、社会的にも職務発明が注目されるようになった。
==概要==
特許法は発明を行った者が特許を受ける権利を有すると定めており(特許法29条1項柱書)、会社の従業員が職務上発明を行った場合でも、特許を受ける権利は従業員個人に原始的に帰属する。しかし会社が多額の開発投資を行った結果として生まれた発明について従業者個人が特許を取得することとなれば、会社は開発投資に見合った収益を得られず、開発投資への意欲を失わせてしまう。そこで、原始的に特許を受ける権利を有する従業者との利益のバランスをとるため、会社には通常実施権(後述)が認められており、特許法35条が、従業者・会社双方の貢献によってなされた職務発明ゆえの「利害調整規定」と言われるゆえんとなっている。
また、契約や就業規則|勤務規則の定めにより、職務発明についての特許を受ける権利を従業員から会社に承継することをあらかじめ予約しておくこと(予約承継)も認められており、出願等の煩雑な手続や特許の有効利用の面から、実務上はこちらの方法がとられることが多いが、一般的に会社は従業員に対して社会的に強い立場にあるため、予約承継を認めることによって発明者たる従業員の権利を不当に害するおそれがある。そこで法は、従業員が会社に職務発明についての特許を受ける権利を譲渡した場合には「相当の対価」を請求できることを定めている。これが、特許法の中にありながら、35条が「労働法の一部を構成する」(後述する東京高裁「光ディスク事件」判決など)とも言われるゆえんである。「相当の対価」の額については、会社が一方的に定めることができず、争いがある場合には裁判所がこれを算出し、不足分についての支払を命じることができる(後述する最高裁平成15年4月22日判決)。
このように、「相当な対価」の額は裁判所が最終的に判断することとなるため、会社にとっては、社内の職務発明規定などに基づいて相当と思われる対価を支払っていても、従業員から訴訟を起こされるリスクをゼロにすることができない。そのため、企業関係者の間から職務発明について定めた特許法35条を改正するように求める声が高まり、平成16年の特許法改正で特許法35条4項が改正された上で同5項が追加され、社内規定が不合理と認められる場合にのみ裁判所が対価を算出することとなった。改正の検討作業においては、職務発明の対価を全面的に契約に委ねる案が主に企業関係者から強く主張された一方、学識経験者などの間では従業員の権利を守るために平成16年改正前の規定を維持するべきであるとの主張も根強く、結局、両者の折衷案的な現在の規定に落ち着いた。
平成16年改正によって社内規定等が尊重されて訴訟が減ることを期待する声がある一方、結局は裁判所が対価を算定する制度は残っており、改正前と実質的な差異は少ないと見る見方もある。2005年現在、企業関係者などからは再度特許法35条を改正して対価について全面的に契約に委ねるべきとの主張が依然としてあり、今後の動向が注目される。なお、特許法35条は実用新案法、意匠法において準用されている(実用新案法11条3項、意匠法15条3項)。
出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 GNU Free Documentation License.
「職務発明」に関連するコラム一覧
経営に関する人気コラム一覧
ビジネス用語・経営用語辞典カテゴリ
- 経営や企業に関する用語
- 営業・集客などのマーケティング用語
- 経営関連の法律・制度の用語
- 経理や会計に関する用語
- 財務や経理に関する用語
- 税金に関する用語
- 組織やマネジメントに関する用語
- 年金・保険・労務に関する用語
- 投資や債権に関する用語
- ISOや規格に関する用語
- 基礎経済知識に関する用語
経営者支援コンテンツ
会員メニュー
会員限定のメニューです
気になったページのMyリストへの登録や、経営に役立つ情報メルマガの管理など、さまざまな便利機能がご利用いただけます





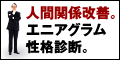 ビジネス向けの無料性格診断で上司と部下の人間関係改善
ビジネス向けの無料性格診断で上司と部下の人間関係改善